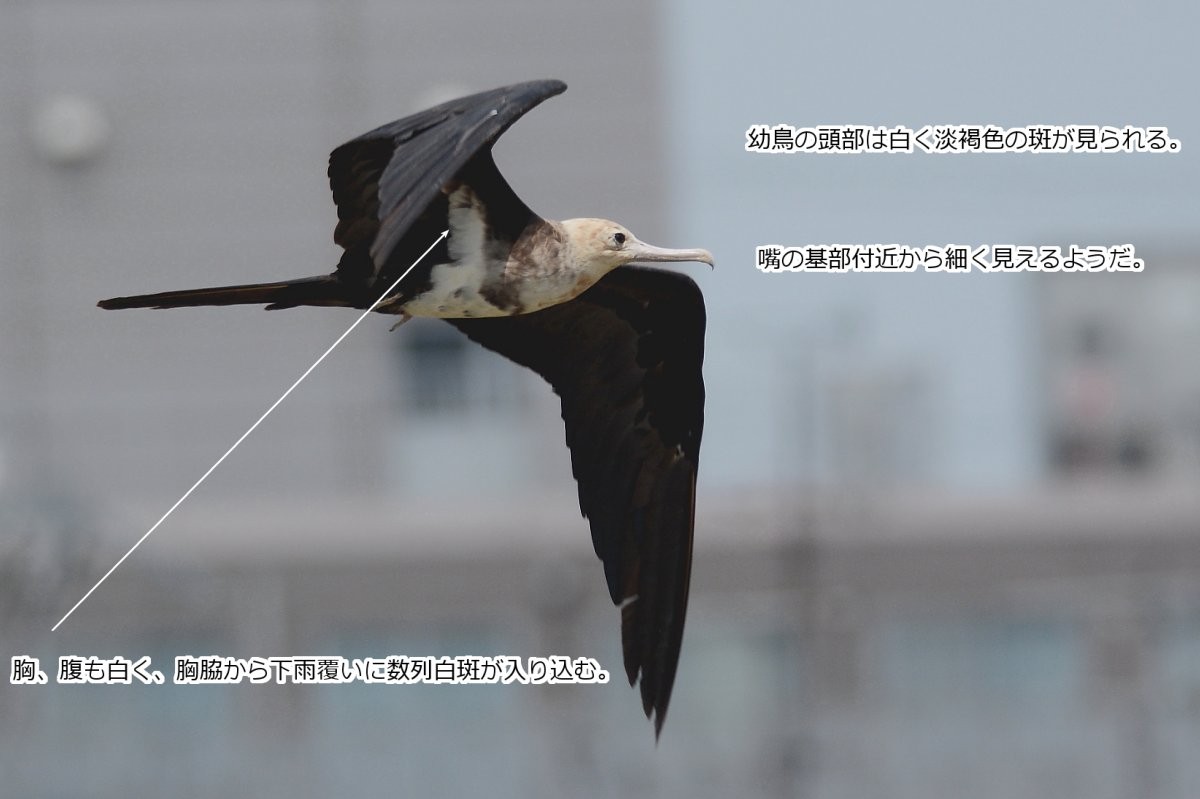日曜日に撮らせてくれなかったのでリベンジに・・・。♀だと聞いてたのですが写真を撮ってみると、嘴基部が黄色いしアイリングにも青みもありませんので、第一回冬羽と思うのですが、さて困った・・・。medaichiには第一回冬羽の♂♀の知識がありません。サンコウチョウの♂第一回冬羽に雄なら雄の何らかの特徴がでるのでしょうか?
日曜日に撮らせてくれなかったのでリベンジに・・・。♀だと聞いてたのですが写真を撮ってみると、嘴基部が黄色いしアイリングにも青みもありませんので、第一回冬羽と思うのですが、さて困った・・・。medaichiには第一回冬羽の♂♀の知識がありません。サンコウチョウの♂第一回冬羽に雄なら雄の何らかの特徴がでるのでしょうか?
春に、短尾でまるでメスのような褐色の体色なのに、嘴もアイリングも立派な個体がいて迷うことがありますが、そんな茶褐色の♀のような体色の♂もいるらしく、紫がかった黒褐色の体色の短尾雄も当然いますので、その前のステージの、第一回冬羽のサンコウチョウは雌雄の区別がつかない場合があるってことになるのでしょうか?
茶色の短尾雄って、雌の体色に擬態することによって、成鳥雄の警戒をかいくぐりすきを狙って繁殖する戦略とか・・・。見慣れたつもりのサンコウチョウもなんか面白そう。どなたかサンコウチョウの第一回冬羽の♂♀について、ご存知の方アドバイスください。