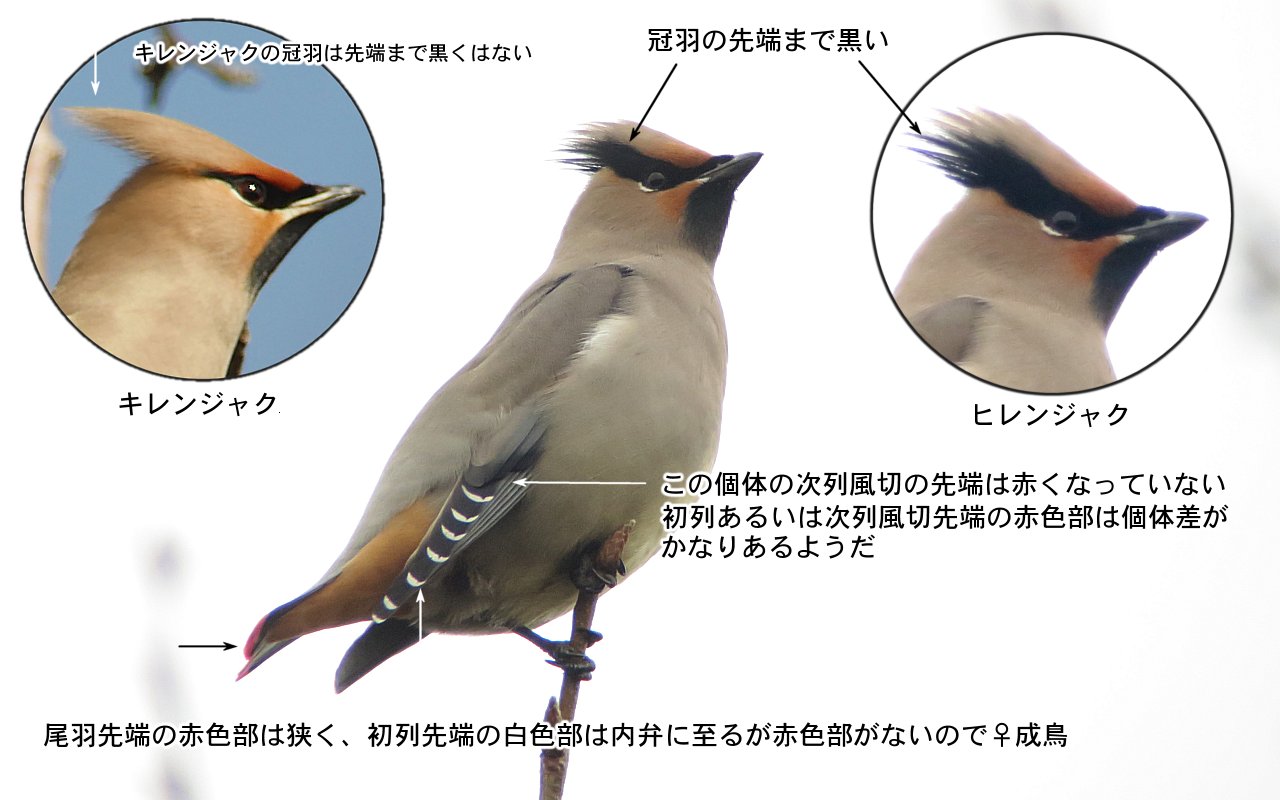ウミアイサは昨年の12月初旬から記録が揚がっていたが、♀と♂1stwしか観てませんでした。明けて1月末ごろから♂も記録が揚がり始めましたが、ほとんど寝てますW。とはいうものの、もう2月も終わり、明日から3月となって尻に火が付いてきました。medaichiとしてはとりあえず写真は押さえておかなければ・・・。
ウミアイサは昨年の12月初旬から記録が揚がっていたが、♀と♂1stwしか観てませんでした。明けて1月末ごろから♂も記録が揚がり始めましたが、ほとんど寝てますW。とはいうものの、もう2月も終わり、明日から3月となって尻に火が付いてきました。medaichiとしてはとりあえず写真は押さえておかなければ・・・。
遠いので気温が上がらないうちに粘ると起きてくれました。おお! 特徴的な胸側の白い班が並んで綺麗です。♂は胸が縦班のある褐色味を帯びますから、他のアイサと間違うことはないので楽です(他のカワとかコウライとか来ないけど・・・)。
 そうですよね。ウミアイサ♂なら特徴的な求愛行動を撮らんといかんですよね。粘ると首を上に上げて「ゴアッ」ってやってくれました。この後、頸を水面まで下げて頭を空に向けるのですが、見事に撮り損ねましたw。ん~、「ご愛嬌で済むか!」っていわれそう。
そうですよね。ウミアイサ♂なら特徴的な求愛行動を撮らんといかんですよね。粘ると首を上に上げて「ゴアッ」ってやってくれました。この後、頸を水面まで下げて頭を空に向けるのですが、見事に撮り損ねましたw。ん~、「ご愛嬌で済むか!」っていわれそう。